| 元捕虜の訪日記録 |
イギリス兵元捕虜の生野訪問
戦時中、兵庫県生野銅山の捕虜収容所で働かされていた、元イギリス兵捕虜4人と家族4人が、終戦からちょうど59年目にあたる2004年8月15日、生野を再訪した。彼らは、(捕虜の時代を除いて)いずれも初来日である。
元捕虜の氏名・年齢・軍隊時代の階級
Eric Robinson (1922年生まれ)
元R.A.F(英国空軍)Leading Aircraftsman(飛行兵長)
George Dunbar (1920年生まれ)
元R.A.F(英国空軍)Corporal(伍長)
John Phillips (1916年生まれ)
元R.A.F(英国空軍)Flight Sergeant(飛行軍曹)
Robert Pogson (1922年生まれ)
元R.A.F(英国空軍)Aircraftsman 1st class(一等飛行兵)
同行した家族
Steve Pogson (51才、Robert息子)
Norman Pogson (49才、Robert息子)
Andrew Phillips (57才、John息子)
Bunty Baldu (64才、Georgeパートナー)
日程
8月10日(火)ロンドンから成田空港着。伊吹が東京のホテルで迎える。
8月11日(水)中尾が東京のホテルでインタビュー。
8月12日(木)午前中、横浜の英連邦軍戦死者墓地に参拝。
伊吹、長沢、田村、東海林、笹本、石井、高田が同行。
戦時中、東京から生野へ疎開していた安井かおるさん(当時5才)も同行。安井さんは、お母さんが英語の先生だったこともあって、捕虜たちと仲良くなり、一緒に写した写真なども保管されていたが、今回のイギリス人一行にそれを見せたところ、写真の人物の名前が判明した。
午後は、浅草などを見物。伊吹、高田、東海林が同行。
John Phillips氏は、父君が明治〜大正にかけて、日本の商船学校や日本郵船で勤務されており、今回、当時の書類を持参された。長沢が同行して、横浜の日本郵船歴史博物館を訪問したところ、貴重な資料だということで、寄贈することになった。
8月13日(金)東京見物など
8月14日(土)東京から京都着、京都市内観光。福林、平田が同行。
8月15日(日)京都から生野訪問。福林、平田が同行。町役場の職員や町の人たちの出迎えを受け、役場のバスで生野鉱山・収容所跡地などを訪問。「毎日新聞」、「神戸新聞」、「読売新聞」の取材を受ける。当時を知る町の人たちの話も聞いた。
8月16日(月)京都発、東京・成田へ
8月17日(火)成田空港から帰国
捕虜になった経緯と日本への移送
彼らはいずれも英国空軍の兵士で、1941年末にシンガポール防衛に派遣されたが、1942年2月、シンガポールが陥落したため、オランダ船に乗って退却する途中、日本軍の潜水艦によって撃沈されて捕虜になり、ジャワ島の収容所で1年3ケ月間捕虜生活を送った。その後、再びシンガポールのセララン収容所に送られ、チャンギー飛行場の整備作業などに従事させられた。
1943年秋、松江丸?に乗船し、日本国内に移送されることになった。船内での待遇はひどいものだった。そのうえ、船がアメリカの潜水艦にねらわれ、台湾の港に逃げ込んだが、捕虜たちはその間1週間ぐらい船倉に缶詰状態におかれるなど、とても苦しい航海だった。
和歌山分所
日本の下関へ着き、そこから汽車に乗って、11月に開設された大阪捕虜収容所和歌山分所(和歌山市松江842)へ送られ、住友金属和歌山製鉄所で働かされた。捕虜の収容人員は約400人で、ほとんど全部イギリス人だった。昼夜3交代で、毎日鉄パイプを作る仕事などをさせられた。
和歌山分所の分所長は、最初のごく短期間は倉西泰次郎中尉、その後は、ナカシセイ中尉であった。
和歌山分所での収容中の死者は、GHQ資料によると18人であったが、彼らは22〜23人ぐらいいたと言っている。彼らは何人かの死者の名前や死亡時の状況をよく覚えている。Alfred Horneという捕虜は、作業中、頭上の滑車が落下してきて直撃を受け、これが原因で死亡した。William Grayという捕虜は、虫垂炎でイギリス軍医が手術をし、成功したが、術後の回復に必要な牛乳がなく、オレンジジュースを代用したところ、どんどん容体が悪くなり死亡した。Cyril Palmerという捕虜は、1944年のクリスマスの翌朝、点呼の時に起きあがってこないまま死んでいた。
生野分所
1945年3月、和歌山分所は閉鎖され(空襲と本土決戦に備える疎開の意味)、捕虜たちは兵庫県の生野銅山に開設された大阪捕虜収容所生野分所(兵庫県朝来郡生野町口銀谷)へ移送され、三菱鉱業の管理下で終戦まで働かされた。
捕虜収容所は、猪野々の谷の社宅街の一番奥に作られた。近くには朝鮮人労働者の宿舎もあった。藤原寅勝著『明治以降の生野鉱山史』(1988年 生野町教育委員会発行)によると、捕虜の宿舎は、立志寮という建物を改造したもので、木造杉皮葺が7棟で647坪、事務所と付属建家は木造トタン葺が4棟で140坪、衛兵詰所と倉庫及び休養室は2棟で80坪であった。その他に外柵工事一式とふとんの購入が行われたという。
兵庫県下の朝鮮人の強制連行を調査している、神戸在住の金慶海氏の聞き取り(『鉱山と朝鮮人強制連行』)とつき合わせてみると、捕虜収容所になった立志寮という建物は、元は朝鮮人宿舎だったものを、捕虜受け入れのために転用したものらしい。
捕虜収容所の跡地は、現在は高齢者用の瀟洒な町営住宅が建っている。元捕虜たちは、その場所を明確に思い出すことができたようで、George Dunbarさんは、谷沿いの道から小さな橋を渡った所が入り口で、警備員の詰所があったと指さしながら教えてくれた。
生野鉱山での労働は、下士官以下の捕虜は、鉱石の採掘、運搬、選鉱作業などに従事し、将校の捕虜は、収容所の菜園などで農作業などをした。John Phillipsさん以外の3人は、坑道内で作業をしたそうで、Robert Pogsonさんは13と15のレベルの層で、Eric Robinsonさんは23という最も深い層で作業をしたが、十分な装備は与えられず、危険がつきまとったという。
現在、生野鉱山跡地には鉱山公園がつくられており、いくつかあった坑道のうちの一本が観光用に残されている。我々は町当局の計らいで無料で中に入れてもらい見学したが、元捕虜たちは昔のことを思い出すのか、所々で立ち止まっては感慨深そうに展示品を見つめる姿が印象的であった。
地元の人たちは、捕虜が3〜4列の隊列を組んで、日本人の監視員に先導されながら、毎日宿舎から鉱山へ働きに行くのを目にしたと話している。
生野分所の分所長は、5月まで藤森アキオ少尉、5月から終戦まで鳴和ヒデオ大尉であった。終戦時収容人員は440人(イギリス383、アメリカ44,オランダ1、オーストラリア8、カナダ2,ニュージランド2)で、収容中の死者はなかった。また、収容所関係者で戦犯に問われた者もいない。
終戦後間もなく、米軍の輸送機が上空に飛来し、パラシュートで救援物資を投下した。空一面に開く無数のパラシュートを見て、捕虜たちは狂喜し、その後、着地した物資に向かって殺到する光景がみられた。物資の一部は、収容所からかなり離れた所にも落ち、住民がそれを拾って隠し持っていたという例もあった。
捕虜たちは町の中を自由に出歩けるようになり、当初、町当局は住民に警戒を呼びかけるなどしたが、さしたるトラブルもなく、捕虜が住民と物々交換したり、親切な人の家を訪ねるなどの交流も生まれた。
1945年9月9日、捕虜たちは生野駅から特別列車で横浜に向かい、帰国の途についた。
捕虜生活の思い出
彼らも、多くの元捕虜と同じように、3年半に及ぶ捕虜生活の精神的後遺症というものは、やはりあったという。Robert Pogsonさんは今日に至るまで、息子たちにも自分の体験をほとんど話さなかったという。
東南アジアの収容所では、捕虜が日本兵に斬首されたり、日本刀の試し切りで殺されるのも見た。日本の収容所では、そこまでひどい残虐行為はなかったが、和歌山の収容所も惨めだった。それに比べると、生野の収容所はまだましだった。とは言うものの、監視員による殴打は絶えなかった。
Pogsonさんは、親切な日本人を2人覚えている。和歌山の収容所では、ある時、英語のわかる製鉄所の従業員が、「苦しい思いをさせてすまない」と言って、Pogsonさんに新しいタバコを一箱くれた。しかし、その従業員の生活状態も、捕虜と変わらないぐらい苦しそうだった。生野鉱山では、Pogsonさんと同じ場所で働いていた日本人の技師が、昼食の時、腐りかけたようなPogsonさんの弁当を見かねて、それを川の中へ捨てさせて、自分の弁当を半分分けてくれた。
生野は、山の緑と、折々に咲く椿、桜、名も知れぬ花などが美しい山間の町で、心が癒されたという。
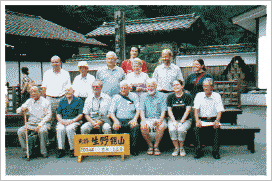 |
 |